2023年末で廃止されたジュニアNISA。
「子どもたちのために育てた非課税の資金を、親の口座に動かすことは、どう動かすか?」と考えました。
片方の子供に沢山お金が入っていて、兄弟の教育費の格差是正を考えました。
親の口座への資金移動を考えた時、色々調べると「名義預金」とか、「相続税」とか、ややこしい話になりそうだったので、調べました。
遡及課税リスクはある?
まず「過去の利益に遡って課税されるのではないか?」という点から始めます。
具体的には、兄弟の教育費の格差是正や親の口座への資金回収のためにジュニアNISA口座を廃止し、資金移動した場合に、「親が本来のジュニアNISAの目的(子どもの将来のための資産形成)とは異なる利用をしたとみなされ、遡及課税されるのでは?」というリスクについて調べました。
- 結論:遡及課税リスクは無いと考えて良さそうです。
ジュニアNISAは2024年1月1日の税制改正により、18歳未満であっても口座を廃止して資金を全額払い出す際のルールが明確化されました。
▶︎ [参考:金融庁 ジュニアNISAの改正に伴う払い出し制限撤廃に関する情報]
- 改正内容: 年齢や理由に関わらず、口座廃止時の過去の非課税利益に対する遡及課税リスクは撤廃されました。
これにより、「ジュニアNISA口座を廃止し、兄弟の教育費の格差是正や親の口座への資金回収」という資金移動の行為自体が、税制上のペナルティを受けるリスクは、無いと考えて良さそうです。
『名義預金・相続税リスク』
遡及課税の不安は消えましたが、次に立ちはだかるのが、「親の相続財産が増える」ことによる実質的な損失リスクです。
親が子どもの資金を回収する行為の税務上の解釈
前提として、ジュニアNISA口座を廃止後、資金は、その子名義の口座に払い出されます。
この資金は、税務上の基本的な考え方(国税庁タックスアンサーNo.4403など)に基づき、そのままでは親の財産とされません。
よって、ジュニアNISA口座による資金は、安全に、その子に相続することが可能となります。
しかし、親がこの資金を親自身の口座に戻す場合、「親が管理・使途を決める」行為とみなされ、税務上「名義預金」と認定されますから、親の相続財産に加算されるリスクに結びつきます。
よって、親の口座に資金移動する行為は、基本的には、本来ジュニアNISA制度により合法的に相続できる権利を、放棄する行為になります。
判断:結局どうする?
まず、ジュニアNISAの資金を子に相続するかどうか?
相続する場合は、そのまま運用継続。
相続しない場合は、資金移動を考えることになります。
資金移動の注意点:贈与税
贈与税は、「財産をあげる側」ではなく「財産を受け取る側(受贈者)」で課税されるのが基本的な考え方です。
- 非課税限度額(基礎控除):贈与税には、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額から、110万円を控除できる基礎控除があります。
受け取った合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(申告も不要です)。
したがって、子ども口座から資金移動する場合、「親が1年間に受け取った贈与額の合計」が110万円以下であれば、贈与税は実質的に発生しないという理解です。
具体的には、両親にそれぞれ対象の1年間で、110万円以下で資金移動し、その他に贈与の受取が無ければ、基本的には、贈与税無しで資金移動できる理解と考えられます。
ジュニアNISA口座解約(廃止)の具体的な手順
一般的な手順を確認しておきましょう。
2024年以降は払い出し制限が撤廃されたため手続きは簡素化されましたが、「全額払い出しが原則」というルールは変わりません。
- 必要書類の請求:利用していた証券会社のウェブサイトかコールセンターで、「ジュニアNISA口座廃止届出書」を親権者(法定代理人)名義で請求します。
- 書類の記入と返送:払出先口座の情報:資金の振込先として、その子の名義の銀行口座を指定します。
- 資金の払い出し:証券会社側で保有商品が全て売却され、口座が廃止された後、指定したお子さま名義の口座に資金が全額振り込まれます。
注意点: 一度口座を廃止すると再開設はできません。また、口座内の資金は全額払い出す必要があります(一部のみの払い出しは不可)。
※免責事項
筆者は税理士・会計士等の専門資格を保有しておりません。本記事は、税務に関する個人的な体験談であり、特定の状況への税務アドバイスを提供するものではありません。必ずご自身の責任において、税理士などの専門家にご相談の上、ご判断ください。
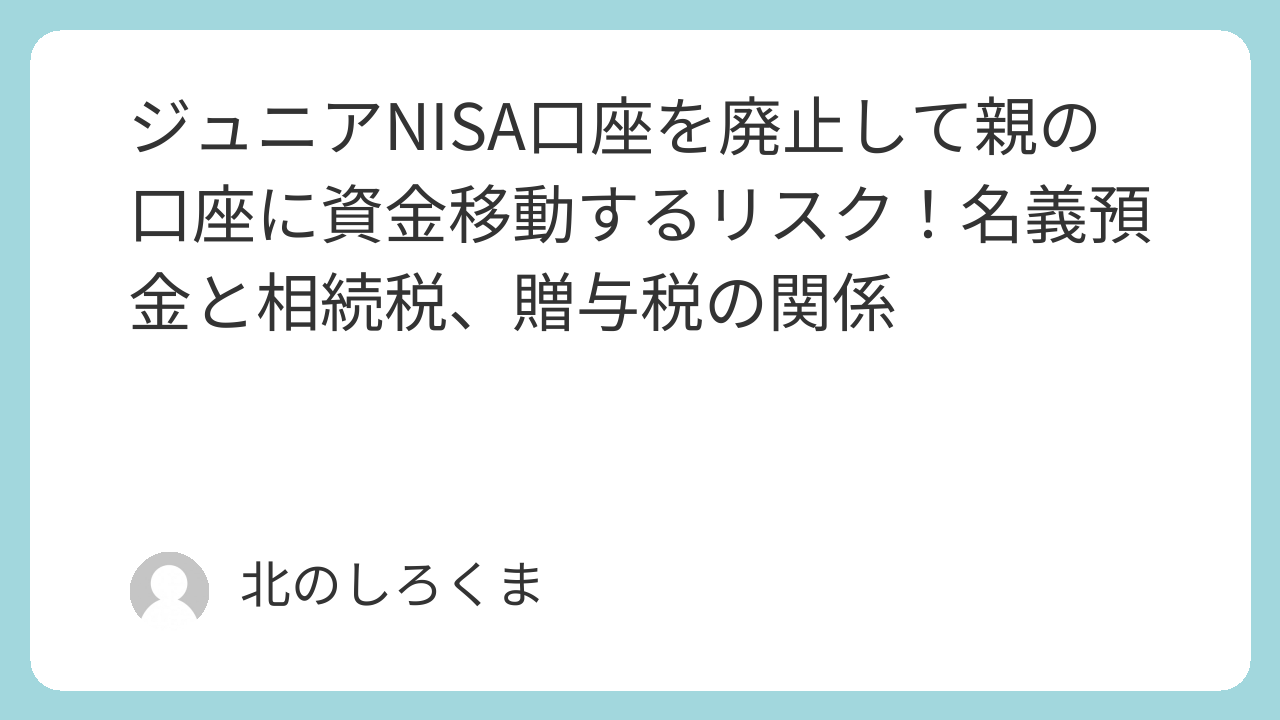
コメント