こんにちは、しろくまパパです。
保険は多くの人にとって『安心』を買うための大切な手段です。しかし、本当にその保険はあなたの人生に必要不可欠でしょうか?私は社会保険労務士事務所で働く中で、「保険に入れば安心だけど、貯金が減る…」というジレンマに直面する方を多く見てきました。
この記事では、保険という「安心感」を、論理的に分解していきます。そして、あなたのライフプランに合った『保険の方程式』を一緒に考えていきましょう。
1. 保険が『安心』をもたらすという、その論理を分析する
なぜ人は保険に入るのでしょうか?多くの人が「万が一の時のため」「安心のため」と答えます。この『安心』という概念を、人事労務のプロとして論理的に分解してみましょう。
病気やケガの経済的負担を軽減
民間の医療保険に入る前に、まずは公的保険制度を理解することが重要です。健康保険には「高額療養費制度」があり、一定額以上の医療費は自己負担額が抑えられます。ほとんどのケースで、この制度が大きな経済的リスクをカバーします。
死亡時に残された家族を守る
万が一の時、残された家族を守るための公的制度として、「遺族年金」があります。民間の死亡保険を検討する前に、公的年金制度でいくら受け取れるかを把握することが、最も論理的な手順です。
節税効果は『期待薄』
保険料控除による節税効果は、給与計算を扱う人事のプロから見て、ほとんど期待できません。生命保険料控除は「所得控除」であり、その効果は限定的です。節税目的で保険に入るのは、まるで『1円を拾うために100円を落とす』ような行為だと理解しておきましょう。
2. 民間保険が抱える『不確実性』というデメリット
保険は安心を買うものですが、その裏には多くの『不確実性』が潜んでいます。
保険金の支払い拒否・遅延
保険金を支払うかどうかは、保険会社の一存で決まることがあります。実際に保険給付の対象となっても、支払い拒否や遅延、不十分な支払いが行われるケースも存在します。
限定的な補償範囲
民間の保険は、公的保険のように広範囲をカバーするものではなく、三大疾病などの特定の病気に特化していることが多いです。
高い『手数料』の存在
私の経験から言うと、保険のセールスマンは、保険契約数に応じた歩合制の給与体系であることがほとんどです。私たちが支払った保険料の一部は、彼らの給料や会社の利益に変わります。これは、保険という商品に、見えない『手数料』が含まれていることを意味します。
3. 知らないと損する!保険の『裏側』にあるお金の仕組み
保険会社が加入者から受け取った保険料を、ただ貯めているだけではないことをご存知でしょうか?
預かった保険料を運用して増やす
保険会社は、私たちが支払った保険料を株式や債券で運用し、利益を上げています。過去20年間の年率リターンは海外株式で9.1%、国内株式で5.7%です。
私たちが銀行に預けても、ほとんど利子はつきません。しかし、保険会社は私たちのお金を運用して増やすことで、大きな収益を得ています。
4. 誰でも達成可能!あなたの『人生の保険方程式』
さて、ここからが本題です。私はこの「知らないって怖い」と思った経験から、「保険会社に支払うお金を自分で運用する」というシンプルな『方程式』を導き出しました。
多くの人が生命保険に支払う保険料の平均額は、年収400万円の世帯で年間約30万円です。この金額を保険会社に払う代わりに、自分で運用するとどうなるか試算してみましょう。
目標設定:
年間30万円の保険料を、自分で積み立てる。目標額は、死亡保険金相当の1000万円。
『方程式』の解き方:
もし、毎月2.5万円をただ貯金するだけなら、1000万円貯めるのに33年以上かかります。
しかし、これを年率5%で運用すれば、約20年で1000万円に到達します。
さらに、年率9%で運用できれば、わずか14年で1000万円を達成する可能性があります。
節税しながら資産を運用するならこちら→【新NISA・iDeCo】理系パパの論理的活用術。eMAXIS SlimS&P500で迷わない資産形成
URL:https://kitano-shirokuma.com/nisa-ideco-strategy/
5. 【結論】公的保険+自分に合った補完策、最強の『方程式』
民間の保険に入る前に、まず公的保険制度(遺族年金・高額療養費制度など)を理解し、それでカバーできない部分を把握することが、最も論理的なステップです。
そして、その不足分を補うために、「保険会社に支払うお金を自分で運用する」という選択肢があります。
iDeCoは、節税メリットがあり、60歳未満で死亡した場合には積立金が死亡一時金として遺族に支払われるため、死亡保険としての代替性も期待できます。
自分で運用するのが不安な場合は、掛け捨て型の生命保険という選択肢もあります。貯蓄性のない分、保険料が安く、必要な期間だけ必要な保障をピンポイントで確保できます。特に、子供が自立するまでの間だけ保障が欲しい、といった場合に有効な手段です。
保険の安心感を買うのではなく、自分で知識と資産を積み重ねることで、本当の『安心』を手に入れることができます。
このブログが、あなたの保険に対する考え方を変えるきっかけになれば幸いです。
【関連記事】
まだ読んでない方はまずはこちらの記事をご覧ください→「お金のロジックツリー」
URL: https://kitano-shirokuma.com/money-logic-tree/
マイカーを持たない暮らしで資産形成を加速させたい方はこちら→「マイカーを持たない暮らし」
URL: https://kitano-shirokuma.com/car/
話題の大学無償化について→「大学無償化のメリットデメリット」
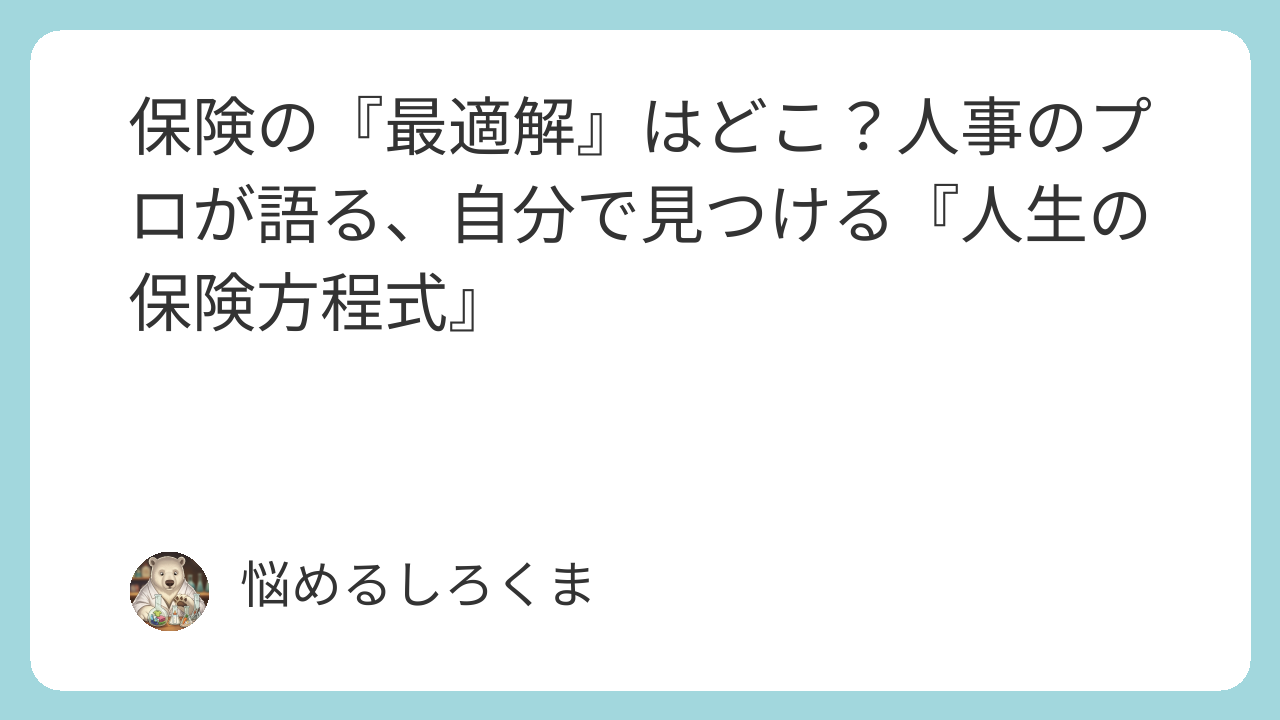
コメント