「3人以上の子供がいる家庭は、大学無償化!」
このニュースを聞いて、子供を持つ親として、期待と不安が入り混じった方も多いのではないでしょうか。我が家にも子供が2人いるので、一瞬「もう一人作るか?」と本気で考えてしまいました。
しかし、この制度をよく調べてみると、私の結論は「なーんだ、これなら3人いる方がお金も子育ての労力も使うじゃん、やーめた」でした。
なぜなら、安易に「無償化」という言葉に飛びつく前に、知っておくべき「落とし穴」が隠されているからです。本記事では、この制度のメリットとデメリットを、最新の情報を踏まえた我が家の具体的なシミュレーションを交えながら、徹底的に解説します。
1. 多子世帯の大学無償化、その概要と落とし穴
多くの人が「大学無償化」と呼んでいるこの制度は、2020年度に創設された「高等教育の修学支援新制度」の拡充版です 。そして、その拡充は段階的に進んでいます。
令和6年度(2024年度)の拡充: 世帯年収が約600万円までの多子世帯を対象に、支援が開始されました 。ただし、この時点では支援額は満額の4分の1に限定されています 。
令和7年度(2025年度)からの本格拡充: 多子世帯に対する所得制限が完全に撤廃されます 。これにより、年収の多寡にかかわらず、扶養する子どもが3人以上いる世帯が支援対象となります 。さらに、授業料の減免額は満額(国公立約54万円、私立約70万円)に引き上げられます。
一見すると、非常に手厚い支援に見えます。しかし、多くの人が見落としがちな最大の落とし穴が「多子世帯の定義」です。
この制度の適用を受けるには、3人以上の子供を同時に扶養している必要があります 。つまり、一番上の子が大学を卒業して扶養から外れると、その時点で多子世帯の条件から外れ、下の子の無償化支援は打ち切られてしまうのです。
2. 3人兄弟は全員無償化になる?我が家のシミュレーション
では、具体的にどのような家庭が得をするのでしょうか。我が家が実際に計算してみた結果を紹介します。
【シミュレーションの前提】
全員が4年制大学に入学
兄弟間の年齢差によって、大学在学期間が重なる期間が変動する
例1:年子が全員4年制大学に入学した場合
第一子: 4年間無償化
第二子: 3年間無償化
第三子: 2年間無償化
解説: 年子の場合、全員が同時に大学に在学する期間が生まれるため、最も恩恵を受けやすいです。しかし、それでも全員が4年間無償になるわけではありません。
例2:2歳差の3人兄弟が全員4年制大学に入学した場合
第一子: 4年間無償化
第二子: 2年間無償化
第三子: 無償化対象外
解説: 2歳差の場合、第一子が大学4年生の時に第二子が大学2年生になるため、この2年間は無償化の対象となります。しかし、第一子が卒業すると、扶養する子供が2人になるため、第三子は対象外となります。
例3:10歳、5歳、2歳の3人兄弟が全員4年制大学に入学する場合
第一子: 4年間無償化
第二子: 無償化対象外
第三子: 無償化対象外
解説: 兄弟の年齢が離れている場合、大学在学期間が重ならないため、下の子は無償化の対象になりません。
このように、この制度の恩恵を受けるのは、兄弟の年齢が近く、かつ大学在学期間が重なるケースに限られます。そのため、多くの3人兄弟家庭では、第一子しか無償化の恩恵を受けられないという現実があります。
3. 大学無償化、知っておくべきメリットとデメリット
この制度のメリットとデメリットをまとめました。
【メリット】
所得制限がない(2025年度から): これまで支援を受けられなかった高所得の多子世帯も、支援の対象になります。
最大約70万円の免除: 授業料・入学金の負担が大幅に軽減されます。
【デメリット】
恩恵は限定的: 多くの家庭では、第一子しか無償化の恩恵を受けられません。
不公平感: 兄弟の年齢差によって、支援額に大きな差が出ます。
浪人・留年で打ち切り: 留年した場合、支援は打ち切られます。2年以内の浪人は対象となりますが、学業不振による留年は支援対象外です。
さらに、この制度の対象となるには、「学ぶ意欲がある学生」であることが継続の条件とされており、その評価は厳格です。具体的には、以下のいずれかに該当すると支援が打ち切られる可能性があります。
- 修得単位数が標準単位数の6割以下
- 出席率が6割以下
- 警告要件に2回連続で該当(GPAが基準を下回るなど)
4. 結論:教育資金は「制度」に頼らず、自力で準備すべき
「大学無償化」は確かに家計の助けになりますが、その恩恵は非常に限定的です。制度に安易に期待するのではなく、自分でしっかりと教育資金を準備することが、お金の不安を解消する最も確実で論理的な方法です。
そのために最も効果的なのが、新NISAを活用した資産形成です。
節約で投資資金を捻出し、新NISAを使って効率的に資産を増やす。これが、変化の激しい時代でもお金の不安なく子育てをするための、最強の解決策です。
よくある質問(FAQ)
Q. この制度は所得制限がないの?
A. 令和7年度(2025年)からは、多子世帯については所得制限が撤廃されます。ただし、2024年度の支援には世帯年収約600万円という所得制限がありました。また、所得制限はありませんが、資産要件(世帯資産3億円未満)を満たす必要があります。
Q. 浪人や留年したらどうなるの?
A. 留年した場合、支援は打ち切られます [7]。浪人は2年以内であれば対象となる可能性があります。しかし、「学ぶ意欲」が問われるため、出席率が6割以下や修得単位数が標準単位数の6割以下になった場合も、支援が打ち切られる可能性があります。
Q. 2人兄弟の家庭には全く関係ない?
A. いいえ、そうとは限りません。この制度の対象外であったとしても、ご自身の家庭が世帯年収の基準を満たしている場合、現行の高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金・授業料減免)が利用できる可能性があります。また、より高い専門性を身につけたい学生向けに、私立の理工農系学部の学生には年収600万円までを対象とした支援制度が始まっています。
【参考】厚生労働省
高等教育の修学支援新制度(大学無償化)について、厚生労働省のウェブサイトでは、制度の概要や対象者、支援内容に関する詳細な情報が掲載されています。特に以下の資料は、制度の目的や仕組みを理解する上で役立ちます。
高等教育の修学支援新制度について:https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000748217.pdf
「学びたい気持ち」を支援する高等教育の修学支援新制度:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001416191.pdf
【参考】日本学生支援機構(JASSO)
日本学生支援機構(JASSO)は、この制度における奨学金の運営を担っています。給付型奨学金や授業料減免に関する具体的な申請方法、スケジュール、必要書類など、実務的な情報が豊富に提供されています。
JASSO奨学金ホームページ:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
このページから、「高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金+授業料等減免)」の特設ページにアクセスできます。
大学無償化は非常にありがたい制度ですが、残念ながら万能ではありません。特に、私立大学の授業料や、一人暮らしにかかる費用は、制度だけではカバーしきれないのが現実です。
だからこそ、制度に頼りきるのではなく、自力で資産を築くことが重要になります。
そのための最も合理的で、低リスクな選択肢が新NISAです。
新NISAを始めるときに読んでおきたいのがこの本です。
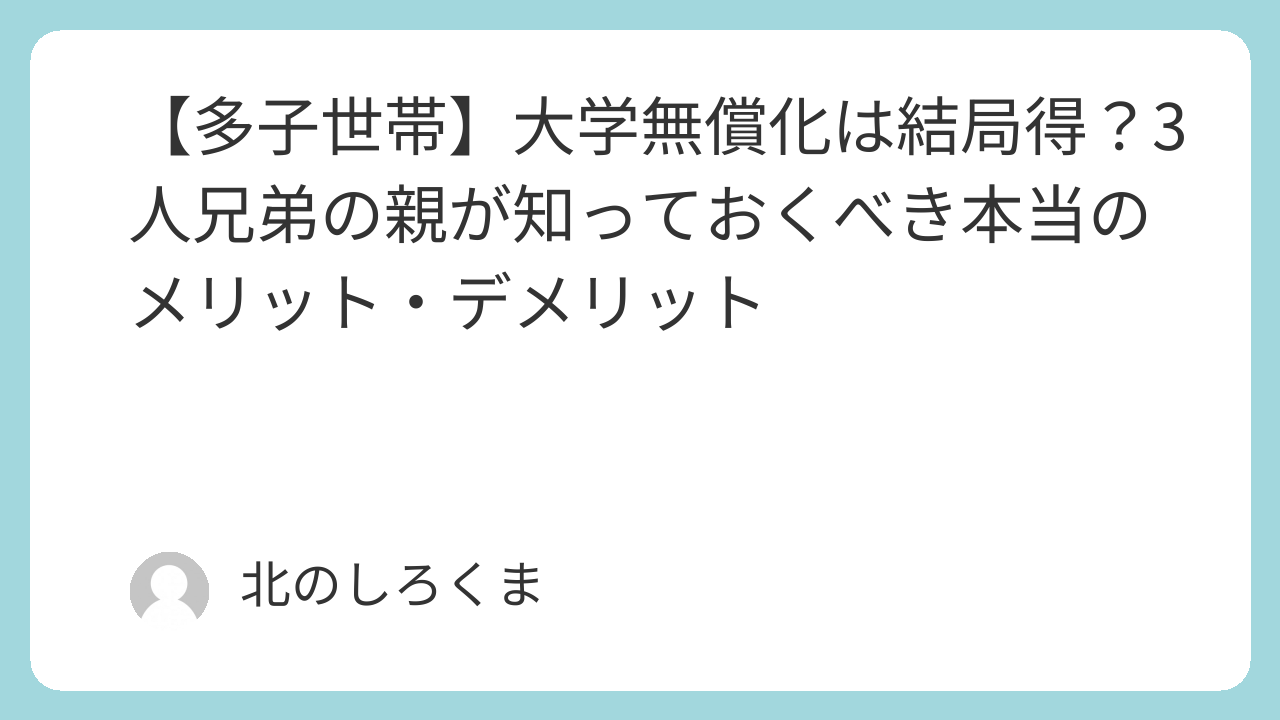
コメント